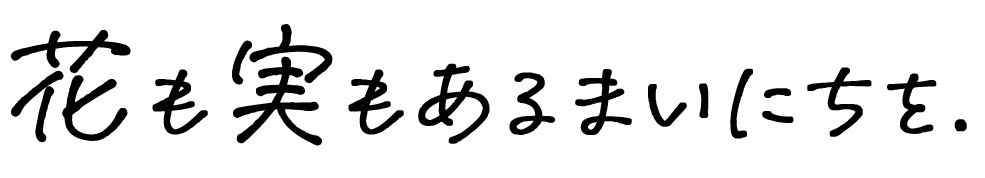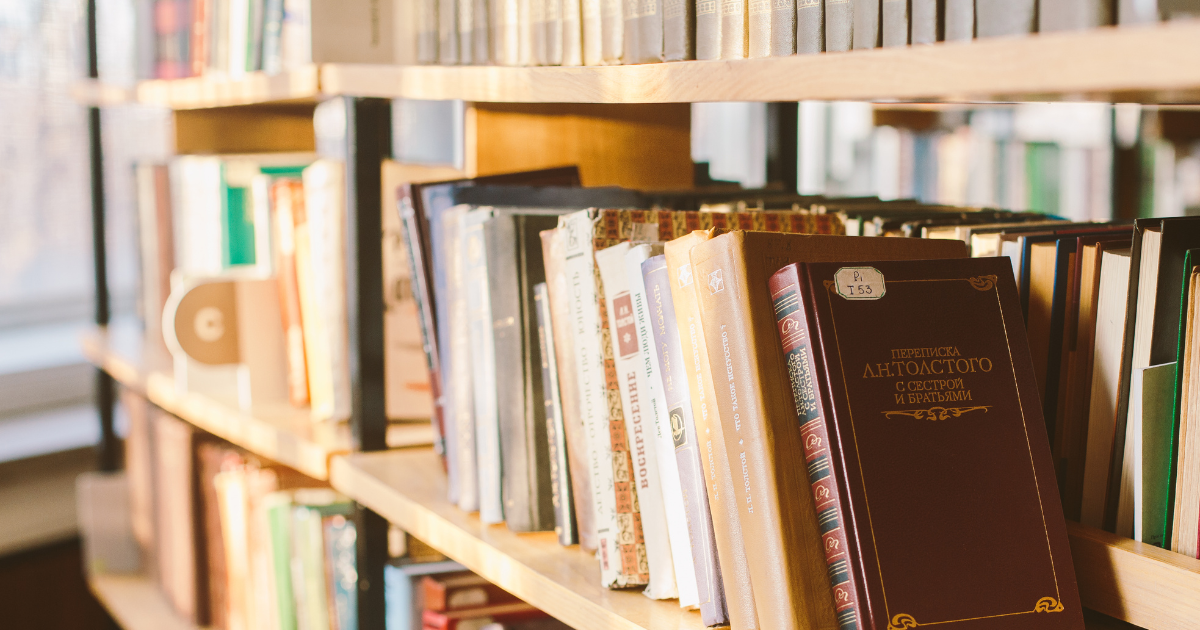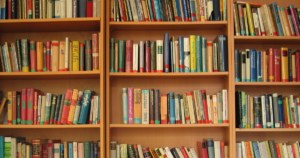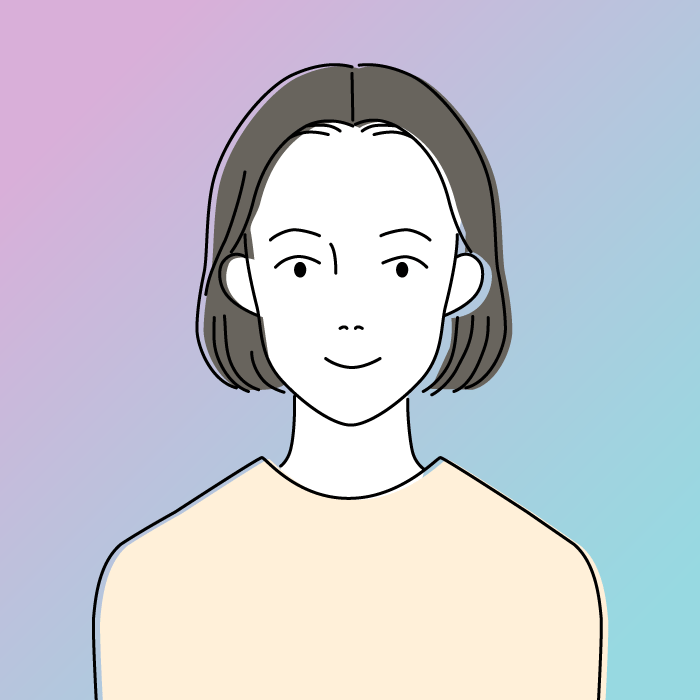「世界一やさしい問題解決の授業」がどんな内容なのか知りたい
「世界一やさしい問題解決の授業」を読んだ感想を知りたい
「世界一やさしい問題解決の授業」は本当に効果があるのか知りたい
本記事では、そんな方のために、40代ワーママ・シンママの明(あかり)が、中高生に理解できる形で「問題解決」について教えてくれる書籍「世界一やさしい問題解決の授業」について解説し、その感想をシェアします。
「世界一やさしい問題解決の授業」ってどんな本?
「世界一やさしい問題解決の授業」の著者は米イェール大卒、外資系コンサルのマッキンゼー出身というご経歴の渡辺 健介氏です。
本書は3つの章からなっており、 目次は以下の通りです。
- 1限目 問題解決能力を身につけよう
- 2限目 問題の原因を見極め、打ち手を考える
- 3限目 目標を設定し、達成する方法を決める
「中高生でも分かる授業」というコンセプトに沿って、章立ても「1限目」という学校の授業風になっています。
1限目では、そもそも問題解決とはどんなことをすることなのか?できるようになるとどんな良いことがあるのか?といった意義の部分と、問題解決の流れの全体像について説明されます。「問題解決力がつくとこんなに進化できる」というくだりを読むと、すごい!自分もそうなりたい!と素直に思える内容です。
2限目・3限目ではそれぞれ問題解決と目標達成の具体的な手法を中学生のバンドのキノコちゃんたちやパソコンを手に入れたいタローくんの事例に沿って解説されます。出てくる単語は「校内新聞」や「お手伝い賃」など、ほのぼのするのですが、分析や思考の進め方は骨太です…!
「世界一やさしい問題解決の授業」の感想
私は、これまで日本の平均的なホワイトカラーワーカーが集まる会社で働き、そういう家族や友人に囲まれて日常生活を送っている中で思うのですが、何か問題があっても解決策が見つからず、そのまま放っておかれている場面は結構多いように感じます。論理的な問題解決思考に基づき、解決策を見つけて行動する、という意思決定を、みんなが当たり前にできる、というわけではないのが今の私の周りのリアルかなと思います。
仕事の場面では、そういった状況が事業がうまくいかないことに直結するので特に深刻ですが、そもそも多くの社会人にとって、問題解決の思考が当たり前の常識でないことが問題なのかなと思います。
その大きな原因が、日本で標準的な教育を受けてきた大多数の人にとって、問題解決力を身につける教育やトレーニングが身近でないことなのではないでしょうか。
本書から、問題解決力は外資系コンサルや企業の経営をするビジネスパーソンだけが持つ特別な力ではなくて、学生からふつうのオフィスワーカーまでみんなが持つべきだし、訓練すれば身につけられるスキルだということ、またそういったスキルを身につけた人が増えることで、自分の身近な問題から社会全体の大きな問題まで、さまざまな課題が解決されるより良い社会の実現につながる、というメッセージを感じました。
そして、そのスキルはなるべく早くに身につけるに越したことはない、というのは本当にその通りだと思いました。私も自分の子供がもう少し成長したら、ぜひこの本を一緒に読んで、子供が解決したいトピックの課題解決を実践してみようと思っています。
「世界一やさしい問題解決の授業」は役に立つ?
役に立ちます! 難しい言葉ではなく限りなく平易な表現で(例えば「ロジックツリー」は「分解の木」、「原因の特定と打ち手の決定」は「お医者さんのように診断し、治し方を考える」といった要領です)書かれているので理解しやすく、2限目の事例に出てくる登場人物もかわいいイラストで表現された身近な子どもで、素晴らしくとっつきやすいです。
私自身、ビジネススクールで「問題解決」について学ぶ講座に参加しテキストや演習が難しいな〜と感じて煮詰まった時に、この本を手に取り、頭が整理できて助けられました。
自分の身の回りや関わる仕事で起きている問題を解決する糸口を見つけたい、問題解決力を身に付けたい、という思いをお持ちの方や、子どもに問題解決力を身に付けてもらいたい、と思う方におすすめの一冊です。ぜひお手に取ってみてください。