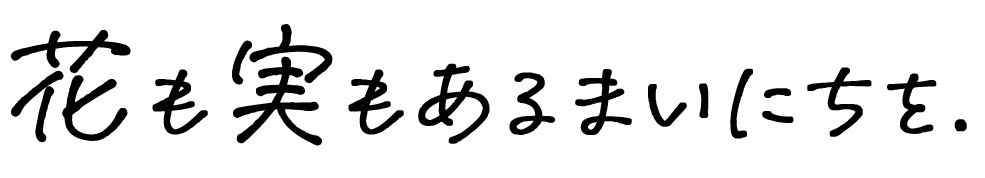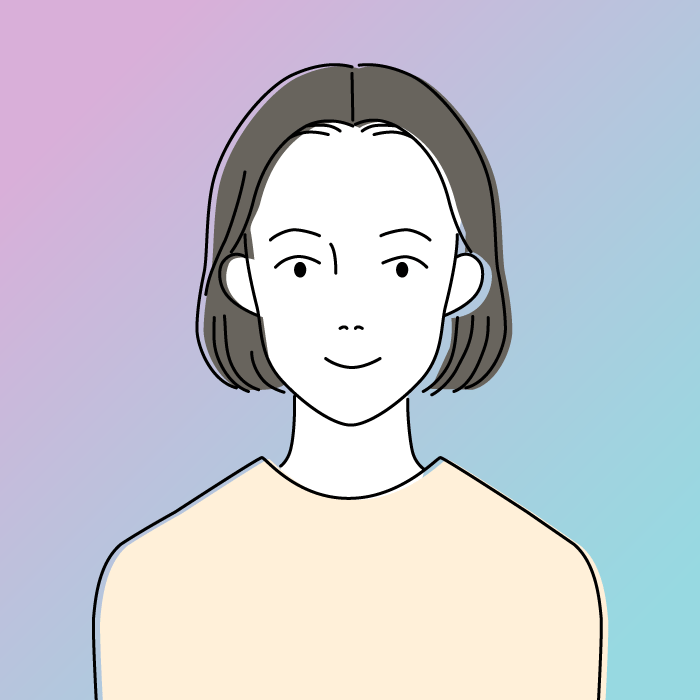「7つの習慣」を会社の上司がおすすめ本として紹介していてちょっと気になる。分厚いし、いくつも本が出ているけど、どんな内容なんだろう?
「7つの習慣」は実際、どんなふうに仕事や生活に活かせるの?そもそもどんな効果があるの?
この記事では、そんな疑問に、40代ワーママ・シンママで、数年前に「7つの習慣」に出会い、日々の過ごし方に「7つの習慣」のメソッドを取り入れ実践している明の経験談を交えて、個人的な所感をお伝えしていこうと思います!
「7つの習慣」とは
スティーブン・R・コヴィー氏によって書かれた書籍「7つの習慣」は、1989年にアメリカで初版が出た後、1996年に日本版が発行され、2020年時点で全世界で全世界4000万部 日本国内240万部発行を突破した自己啓発・人生哲学といったジャンルのベストセラーです。長年多くの人に読まれ続けている代表的な自己啓発本のひとつなので、タイトルは聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
「7つの習慣」は「成功」をテーマとして書かれた本なので、「自己啓発本」というカテゴリーづけをされることが多いですが、内容としては「充実した人生を送る」ための思考や行動指針の本だと思います。私が「7つの習慣」を読んだのは、アラフォーになってから(つまりここ数年)ですが、「7つの習慣」の内容を知ったことで、人生に対するとらえ方が変わり、それをきっかけに、自分の人生の過ごし方について真剣に考え向き合えるようになったと思います。
私のような人に、ぜひ「7つの習慣」に出会って欲しいので、私の思いや実体験をご紹介していこうと思います。
私が7つの習慣に出会ったきっかけ
私が「7つの習慣」と出会ったきっかけは、とある企業の社長が書いた「時間を効率的に使う」というテーマのビジネス書でした。その頃私は、当時の上司に「仕事が遅い」と言われていて「仕事が早くなるためのノウハウが書かれている本」を探し、その本に辿り着きました。
私は、その本に書かれている仕事への向き合い方や仕事術に感銘を受け、さっそく書かれている内容をできるだけ実践したのですが、それと同時に、著者の人生の本質を大事にした仕事のとらえ方や、生き方が的な生き方がとても素晴らしいなと思い、その考え方も見習いたいと思いました。その中で、その方が強い影響を受けた本として紹介されていたのが「7つの習慣」で、これがきっかけで私は「7つの習慣」を手に取ったのでした。
私の「7つの習慣」実践方法
私が実践したのは「7つの習慣」の手帳「フランクリン・プランナー」での時間管理術です。公式オンラインショップを見ると分かるように、フランクリン・プランナーには種類が沢山あるのですが、購入したのは綴じ手帳の「フランクリン・プランナー オーガナイザーA5サイズ」でした。システム手帳タイプのものよりは安価ですが、それでも私には高いな、と一瞬ためらったものの、これは試す価値がある!と思い、購入しました。実際使ってみてどうだったかといえば、日々の計画や時間管理のために、この手帳はとても理にかなっていて手放せない存在となり、その後毎年、冬が近づく時期になると購入して使っています。
自分のミッション・ステートメントを書く
フランクリン・プランナー オーガナイザーには日々の計画のページのメイン冊子に加えて「フランクリン・プランニング・システム」なる、分冊の薄い冊子ページがあるのですが、その中に「ミッション・ステートメント」を書く部分があります。ミッション・ステートメントとは公式サイトによると「あなたの人生がどういうものなのかを表す信念やモットーのようなもの」「人それぞれの生活、行動における憲法」なのですが、自分のミッションステートメントを言語化する作業は、最初の年は、なかなかうまくいきませんでした。「人生の終わりの瞬間をどう迎えたいか」や「自分が喜びを感じるのはどんなことなのか」をイメージし、ゴールを設定し、そこから逆算する形で、自分の人生のありたい姿や、成し遂げたいことを言葉にするのですが、どうも本音でないきれいごとを書こうとしてしまい、なんか違うなあ。。と感じてやめてしまいました。
その後しばらくして、本格的に仕事について悩んだことをきっかけにキャリア・コーチングの講座や、定期的なコーチングを受けるようになり、トレーナーやコーチに内省や自分の思いの深掘りを手伝ってもらうようになったのですが、コーチングによって自分の価値観や、本音が見えてきたことで、最近は具体的な「やりたいこと」が描けるようになってきました。
コーチングも「7つの習慣」と同じく、自分の人生をより良いものにするためにとても役立つものなので、あわせておすすめしたいです。そのお話はまた改めて。
自分の役割を定義する
7つの習慣を読むまで意識していなかったのですが、多くの人は人生の中で複数の集団に属していて、その中でそれぞれ異なる立場や役割があるととらえられるのでないでしょうか。例えば、私の場合で言えば、フルタイムで働いている会社では中堅メンバー、家庭では娘にとっては母親で、複数の「自分の役割」を果たしていくことを期待されています。手帳を使って、1週間単位で予定を立てるにあたって「自分の役割」を定義して、それぞれの役割でどんなふうに役目を果たしていきたいか、そのために何を目標にするかという順番でやることを決めていきます。
私の場合、仕事を大事にすることに集中してしまい、つい子供との関わりをおろそかにしがちだったのですが、娘の母として、どう関わっていきたいのかを定期的に考え振り返ることで、子供と遊びに行く予定や勉強を一緒にやったり、じっくり話を聞く時間を作ろうとする意識が働き、子供と良い時間を過ごせていると感じます。
「刃を研ぐ」習慣を作る
「7つの習慣」では「刃を研ぐ」という概念が出てくるのですが、これはざっくり言うと「心身のコンディションを維持・改善するために行うこと」です。
「刃を研ぐ」習慣とは、運動や食事管理などの健康習慣だけでなく「肉体」「情緒」「知性」「精神」の4つにカテゴリー分けされます。たとえば運動は「肉体」の習慣ですが、「情緒」には好きな人や友達との絆を深める時間、「知性」であれば知識を得るための読書やブログを書くこと、「精神」であれば、自然に触れる時間などがあります。
なんとなく取り入れていた自分のための習慣や時間を「7つの習慣」によって「自分の体や精神という資産」を維持し増やすための大切な時間だととらえるようになり、あらかじめ時間を確保し自分の体や心を健康に保つため、何をしようか計画をたて、これも手帳に書いて予実管理するようになりました。振り返りをすることで、最近「刃を研ぐ」時間が不足しているな、と意識できることが、とてもいいなと思っています。
「第2領域」の予定を優先する
「第2領域」とは人生の活動を「緊急度」と「重要度」の軸のマトリックスに分類したときに「重要だが緊急ではない」に含まれる活動のことです。プライベートで言うと上でご紹介した「刃を研ぐ」の内容がまさに「第2領域」の活動になります。また、仕事の場合は「中長期的な計画」や「スキルアップのための研修や学習」などがこれにあたると思います。
このような活動はつい「急ぎの予定」を優先して後回しにしてしまいがちですが、長い目で見ると、自分の成長や人生の質を上げるための土台づくりのための大切な時間です。そのことを意識して、1週間の予定を立てたり、どちらを優先するかの判断をする際に「第2領域」の予定を優先するようになりました。
自分の身に起きたことを俯瞰する
私が「7つの習慣」を読んで、最も印象に残った内容が「刺激と反応の間にはスペースがある」という一節でした。
これまでの自分の人生で、挫折を感じたり、乗り越えられない壁に出会ったことの多くは、「他者からの評価や反応に傷ついて逃げてしまった」というパターンだったなと思います。
この「刺激と反応の間にはスペースがある」という言葉は「起きたことに対して、自分がどう反応するかは自分で決められる」という考え方です。他者の言うことや行動、出来事をコントロールすることはできませんが、その「刺激」をどう受け止めるかは、自分でコントロールできること。真に受けて、反射的に傷ついたり、ネガティブな気持ちになる必要はなくて、まず自分に起きたことを、文字に書いたりして俯瞰して見てみる、そんな習慣を身につけることで、精神的な負担がとても軽くなり、行動力がついたなと感じています。
7つの習慣の効果
上記のように、私は「7つの習慣」を読み、手帳フランクリン・プランナー オーガナイザーを使うなどそのメソッドを実践することで、「自分の人生に向き合って、限りある人生の時間の使い方を自律」し始めることができたと思います。その結果、ヨガやストレッチで体が柔らかくなったり、スキルアップのためビジネススクールや資格取得に取り組んで、転職して給与アップしたり、良いパートナーにも出会えたりという眼に見える成果も出ましたし、何より、人生の舵取りができるようになり、人生に取り組む姿勢が大きく好転して、昔の自分が感じていた焦りや不安、無力感を感じにくくなり、自信や満足感が得られるようになってきたと思います。
7つの習慣のおすすめの学び方
いろんな種類の関連書籍が出ていて、本も厚いので、どこから手をつけたらよいのかわからない、という方もいらっしゃるかと思います。私の場合、最初に読んだのは、時間管理にフォーカスした「7つの習慣最優先事項」で、その後に「まんがでわかる 7つの習慣」を読みました。まんが版はコアなエッセンスを読みやすく伝えてくれているのと、感情移入することで気持ちが前向きになり読後感が良くおすすめです。物語の舞台がバーということでカクテルのレシピ紹介が出てくるのも楽しいです。
「7つの習慣」の書かれている内容は、とても幅広く本質的な内容なので、そうと書かれていなくても、いろんな自己啓発やスキルアップ方法の中でおそらく参考にされていて、似たような内容が出てくるな〜、とも思うので、一度読んでみて損はないと思います。
多くの方が「7つの習慣」を読んで、より良い人生を切り開く方法を身につけてくれるといいなと思いますし、私もまだまだ理解・実践できていない内容がたくさんあるので、に触れて読み返して、より多くのことを実践していこうと思います。